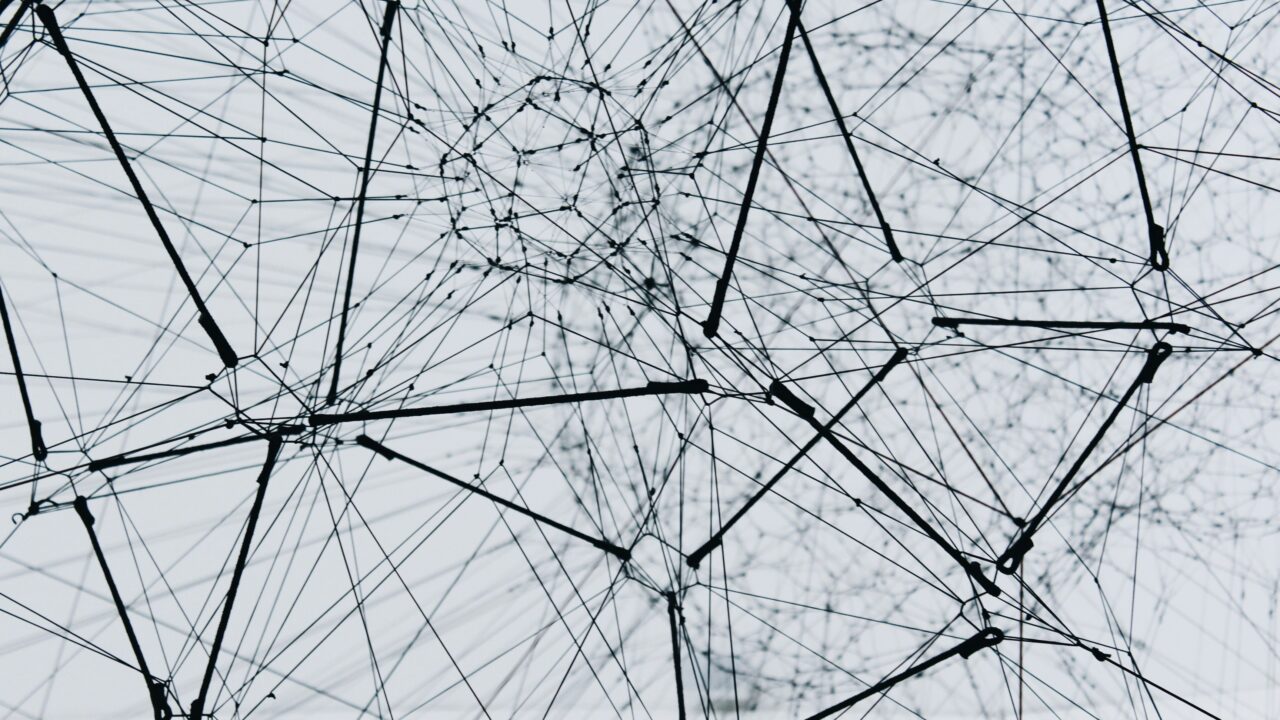あらゆる業界がグローバル志向となっている感じがする。
本当にそれで良いのだろうか。
IT業界でも、いわゆるクライアント・サーバーで、クライアントつまり自身のPCなどの端末とサーバー側の処理で役割分担できていたところで、今はサーバー側の役割が重要になっている。
それはクラウドサービスの勃興であり、PCやスマホが高性能化してきているものの、さらにAI利用とともに、個人情報も、業務情報も、あらゆる資料はクラウド、つまりサーバー側に保管するようになり、サーバー側の役割は重要になる一方だ。
僕の言いたいことは、クライアント・サーバーモデルのことではなく、あらゆる業界がサーバー重視になっていることが気になっていることだ。
サーバー重視、つまりは大事なものが集中管理されているということだ。
確かに、一部で管理したり、サービスしたほうが効率がよいかも知れない。管理する側も、少人数で済むこともあるだろう。
そう、それが問題なのだ。
少人数で全体を管理するには、サーバーモデルが一番やりやすい。頭脳をもつクライアントがたくさんあったら管理しきれないからだ。
しかしそれは全体がいっきに駄目になるリスクをはらむ。リスクを低減させるには、分散するに限る。
すべての国家機能が東京に集中しているとして、東京が天災で壊滅したらどうなるか。
それが国家機能が東京にも、大阪にも、名古屋にも、福岡にも、札幌に分散しているとしたら、それらが同時に天災等で壊滅するとは考えづらいため、リスクは小さくなる。
繰り返すが、少人数で管理したい場合には、分散処理は困る。集中管理のほうが都合がよい。
どうも今の社会は、集中と分散がせめぎ合っているような気がする。
回りくどくなったが、エネルギーも同様だと思う。一箇所で巨大な電力を発電するよりも、分散発電したほうが、天災のリスクが低減する。
いや天災のリスクのみならず、電力輸送のロスが減少する。それなのに、今日本では国内を太い幹線で電力を輸送しようとしている。
まずは、自分で使う電気は自分でつくる。次に地域で使う電気は地域でつくる。その延長が国で使う電気は国でつくる。燃料は輸入しない。
食も同様で、自分が食べる食は自分がつくる。誰でもそれは無理だから、地域で食べる食は基本地域でつくる。その延長で、国で食べる食はその国でつくる。
災害の多い我が国で、それぞれの地域の食とエネルギーの自給率が高いとき、困る人々が少なくなるし、ましてや有事の際には海外からエネルギーや食が入らなくても、国民を守ることができるのではないかと思う。
したがってエネルギーや食は地域単位で考えることが大切なのだと思う。